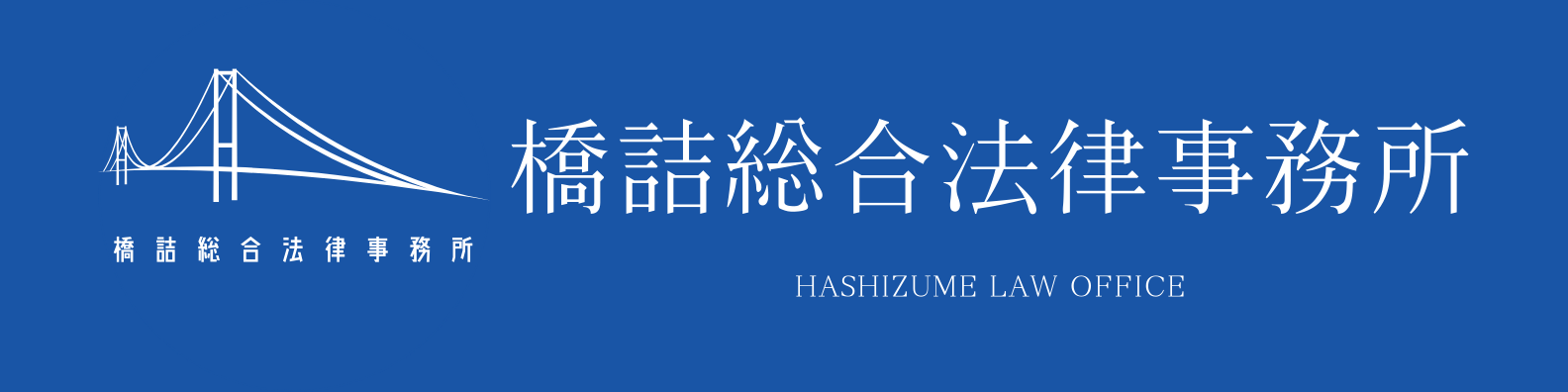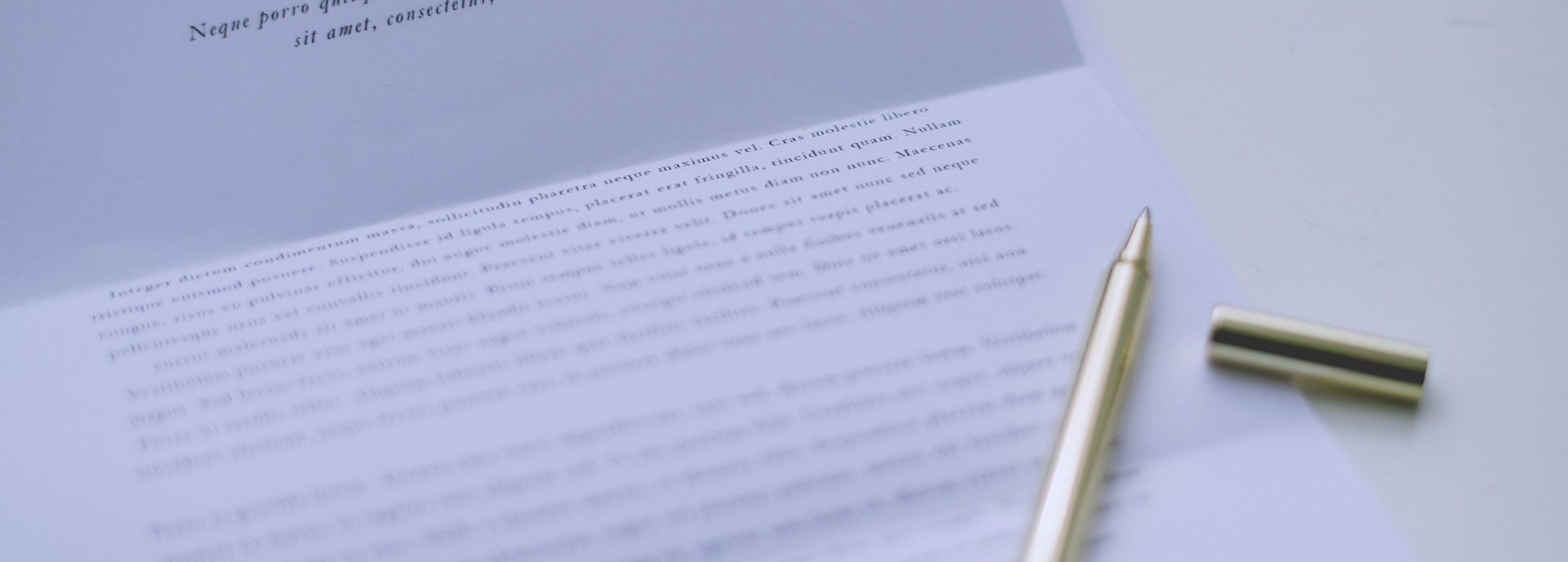1. イントロダクション
- 改正刑事訴訟法が令和6年(2024年)5月15日に施行され、保釈中又は勾留停止中の被告人の監督者制度が新たに創設されました。今回は、法律が改正された内容及び実務への影響を簡潔に説明します。
- 現時点での理解ではありますが、監督者制度は、身元引受人の上位互換的な制度、と言う捉え方をしています。
2. 主要なポイント
- 保釈又は勾留執行停止の場合に、被告人の監督者を設けるという制度が創設されました。
監督者制度は、概要、
・監督者の同意のもと、裁判所が選任する制度である(法第98条の4第1項)
・監督者は、①被告人の逃亡を防止する。②被告人の公判期日出頭確保のための監督をすることが主たる義務である(法第98条の4第3項)
・監督者は、裁判所から③被告人と共に法廷等へ出頭する、又は、④被告人の生活上または身分上の事項について報告することを裁判所から命ぜられる(③又は④の一方又は両方が命ぜられる。法第98条の4第4項)
・監督者は、監督保証金を納める必要がある(法第98条の5、同条の6)
という内容を規定しています。
保釈を請求する場合、これまでは、弁護活動として身元引受人を準備することが通常でしたが、
監督者制度が導入されたことで、この身元引受人との区別をどうするのか、ということが一つのポイントになると思われます。
3. 実務への影響
- 実務上の影響
- 改正が実務にどのような影響を与えるかについて説明します。
上述したとおり、この改正によって、身元引受人との関係がどうなるのか、という点が最も重要な点ではないかと考えています。
一応、裁判所の公式見解は、「監督者制度は、これまで保釈されなかったものの保釈の幅を広げるものである」ということのようです。そのため、この裁判所の見解を前提として考えれば、これまでどおり、身元引受人を準備することを原則としつつ、身元引受人だけでは保釈が難しそうな案件について、監督者を準備することができないかを検討していくこととなりそうです。
- 改正が実務にどのような影響を与えるかについて説明します。
4. 今後の展望と注意点
- 将来的な影響と注意点
今後予想される影響や、留意すべき点について述べます。
1 運用によって、監督者が必須になるようにならないか
この制度が運用された後の懸念点としては、逃亡を防止するための制度ですから、保証金などを納めるわけではない身元引受人よりも、お役所である検察庁や裁判所は、制度としてより安心感のある監督者の選任へと安易に流れていく恐れがあるのではないか、という点です。
例えば、カルロス・ゴーンの逃亡事案のような、センセーショナルな逃亡事件が発生した場合に、裁判所の保釈運用が一気に冷え込んで、監督者がなければ保釈がされにくくなるような状況や、検察官が監督者の選任を強く求めてくるようなことは十分に考えられるのではないかと思います。
検察庁としては、保釈中の逃亡を防止するという名目のもと、従前の運用よりも厳しい保釈の条件等を付すよう意見をしてくるようになり、裁判所がそれに応じて、当初の運用方針、立法の趣旨、というものが有耶無耶にされることが強く懸念されるのではないかと危惧しているところです。
なお、日本保釈支援協会のページによれば、アメリカなど諸外国で同様の制度があり、監督者が選任される割合が6−7割程度になっているとのことであり、このような懸念は、あながち的外れでもないようにも思えています。
2 監督保証金の金額が不明である
現段階では運用が開始されたばかりですので、金額が不明です。
(被告人が支払う建前の)保釈保証金以外に、監督保証金が設定されるわけですが、どれくらいの数字が基準となるのか、という点は、運用を見ていかないと想像がしにくいところと言えるかもしれません。
3 誰が監督者になるのか
法律上は、監督者になれる人の要件などは定められていません。
そのため、誰でもなれるように見えるところではありますが、他方で、身元引受人になる人は、基本的に親族や職場の上司などであることが多いことからすると、必要な場合には、これまで身元引受人になっていた人が、監督者として同意して、保証金などを納めてもらう、ということとなる可能性が高いのではないかと思います。
4 同意をどのように取得するのか
法第98条の4第1項には、「裁判所は、・・・適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。」とあります。そのため、裁判所は、監督者になる予定の者から同意を得る必要があるのですが、これが書面で良いのか、監督者を裁判所に連れていけば良いのか、ということは、実際に利用する場面で確認する必要があると思うところです。
5. まとめ
- 要点の再確認
- 監督者制度の創設に関する要点は、
・(おそらく)身元引受人の上位互換の存在となる監督者制度が設けられたこと
・監督者制度が設けられたことにより、保釈の範囲が広がる余地ができたはずであること
・ただし、運用によっては、保釈が窮屈になりかねない余地もあること
・運用が始まったばかりであることから、具体的な保証金の金額や、報告義務がどの程度の負担になるか、という点は不明な点が残っていること
といった点になると思います。
実際に事件を扱う中で、参考になりそうな情報がありましたら、随時アップしていきたいと思います。
- 監督者制度の創設に関する要点は、
6. 参考文献・リンク
- 法令や関連資料へのリンク
- 新旧対象
https://www.moj.go.jp/content/001391777.pdf - 改正に関する叩き台(制度ごとにまとめられていたため、あえてリンクを貼っています。
https://www.moj.go.jp/content/001357086.pdf
- 新旧対象